お七夜は、赤ちゃんの健やかな成長を願う日本の伝統的なお祝いです!
赤ちゃんが生まれて間もない頃、慣れない育児や体調の変化で、毎日がめまぐるしく過ぎていきますよね。
そんな中で耳にする「お七夜(おしちや)」という言葉。
「やった方がいいの?」「みんなは、する?しない?」と、悩んでいるママも多いのではないでしょうか。
この記事では、「お七夜をする・しない」のリアルな声や、簡単なやり方、おすすめグッズまで、紹介します!
迷っているあなたが、ホッと安心できるヒントになりますように♪
- お七夜とは
- お七夜する派
- お七夜しない派
- いつする?
- やり方
- 簡易的な方法
- おすすめグッズ
お七夜はする?しない?ママたちのリアルな声を紹介!

お七夜ってよく聞くけれど、その意味までは知らないという方も多いですよね。
まずは、お七夜の由来や意味について見ていきましょう♪
お七夜とは
お七夜は、生後7日目に赤ちゃんの名前を決めて祝う、古くからの風習です。
昔は医療が発達しておらず、生まれてすぐに命を落としてしまう赤ちゃんも少なくありませんでした
そのため、生後7日目を無事に迎えられたことを神様に感謝し、今後の健やかな成長を願う意味合いが強かったのです!
お七夜では、主に以下のことを行います♪
現代では、出産を頑張ったママの労をねぎらい、新しい家族の誕生を祝う大切なイベントとして捉えられていますよ!
する派
「一生に一度のことだから、きちんとお祝いしたい」という思いから、お七夜を行う家庭も多いです。
お七夜をすることで、赤ちゃんの誕生を改めて実感し、お祝いの気持ちを共有できるメリットがあります。
また、命名式を行うことで、赤ちゃんの名前を正式にお披露目する良い機会にもなりますよ!
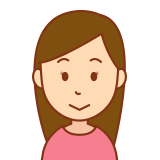
退院後で大変だったけど、夫や両親と協力して準備をしました!
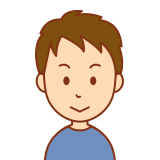
命名書を書いて、みんなでお祝い膳を囲んだことで、新しい家族になったんだなと実感が湧きました。
準備は大変かもしれませんが、家族にとってかけがえのない思い出になるでしょう♪
しない派
「退院したばかりで、体調が万全ではないから無理をしたくない」という理由で、お七夜を行わない家庭も増えています。
出産後のママの身体はボロボロで、休養が必要です!
また、慣れない育児に追われ、お七夜の準備をする精神的・時間的余裕がないのが現状です。
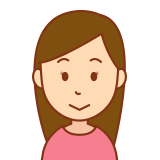
退院したばかりの身体で無理をするより、まずは赤ちゃんのことでいっぱいいっぱいだったので、お祝い膳は後日改めてやることしました!
無理のない範囲で、家族のペースに合わせてお祝いするのが何よりも大切です。
お七夜はいつする?基本的なやり方についても徹底解説!

お七夜は、赤ちゃんの生後7日目の夜に行うのが伝統的です。
「生後7日目に行うもの」と分かっていても、もし7日目にできない場合はどうすればいいのか、疑問に思う人も多いですよね。
お七夜を行うタイミングと、そのやり方について詳しく見ていきましょう!
いつする?
お七夜は、赤ちゃんが生まれた日を「0日目」と数えて、7日目にあたる日に行います。
たとえば8月1日に生まれた赤ちゃんの場合、お七夜は8月7日が目安です。
日付の数え方に地域差はあるものの、厳密でなくてもOK♪
「退院してから落ち着いた週末にやった」「予定日より早く産まれたので、命名はしばらくあとにした」など、柔軟なケースが多いですよ!
体調やスケジュールに合わせて、ママと赤ちゃんが元気であることが一番です。
やり方
お七夜は、大きく分けて「命名式」と「お祝い膳」の2つの儀式を行います。
まず、命名式では、赤ちゃんの名前を家族にお披露目し、命名書に名前や生年月日などを記入します。
命名書は、神棚や赤ちゃんの寝室などに飾りましょう♪
次にお祝い膳では、家族みんなで食事を囲み、赤ちゃんの誕生を祝います。
- 命名式: 命名書に毛筆で丁寧に赤ちゃんの名前を書くのが一般的です。名前の由来や込めた思いを家族に話すのも素敵な時間になります。
- お祝い膳: 赤ちゃんの成長を願う縁起の良い料理(鯛の塩焼き、赤飯、お吸い物など)を用意します。
難しく考えずに、家族のペースで、無理なくできる範囲で行うのがポイントですよ♪
お七夜をする時の簡単な方法は?おすすめグッズも紹介!

「お七夜をしたいけど、準備が大変そう…。」と感じるママも多いですよね。
退院したばかりのママでもできる、簡単でおすすめのお七夜の方法や人気グッズを紹介します!
簡単な方法
頑張りすぎず、家族みんなが笑顔で過ごせるような、簡易的なお七夜を検討しましょう。
すべてを完璧にこなす必要はなく、大切なのは、赤ちゃんの誕生を祝う気持ち♪
手間をかけなくても、心に残るお七夜はできますよ!
・記念撮影だけで済ませる
命名書を準備し、赤ちゃんを寝かせた状態で写真を撮るだけでも十分素敵な思い出になります。
・お祝い膳は仕出し弁当やテイクアウトを利用する
無理して手作りにこだわらず、プロにお任せするのも良い方法です。
・家族写真を撮る
命名書を囲んで、家族みんなで写真を撮りましょう。
無理のない範囲で、家族の状況に合わせて工夫するのが、お七夜を成功させる秘訣です。
おすすめグッズ
簡単な方法でお七夜をしたいあなたのために、おすすめの便利グッズを紹介します!
お七夜の準備を楽にするための便利グッズはたくさんあります。
上手に活用して、ママの負担を減らしましょう♪
命名書セット
用紙と筆ペンがセットになったものが市販されています。
中には、手形や足形も一緒に残せるものもあり、良い記念になりますよ。
レトルトのお祝い膳
赤飯や鯛めしなどがレトルトで売られています。
温めるだけで食べられるので、とても便利です。
写真フレーム
命名書を飾る写真フレームや、赤ちゃんの写真を入れるおしゃれなフレームを用意するのもおすすめです。
便利なグッズを活用することで、準備の手間を省きながら、素敵な記念を残すことができますね♪
お七夜はする?しない?まとめ

- お七夜は、赤ちゃんの健やかな成長を願う日本の伝統的なお祝い
- 「一生に一度のことだから、きちんとお祝いしたい」という思いから、お七夜をする家庭も多い
- 「退院したばかりで、体調が万全ではないから無理をしない」という理由で、お七夜をしない家庭も増えている
- 赤ちゃんが生まれた日を「0日目」と数えて、7日目にあたる日に行う
- 「命名式」と「お祝い膳」の2つの儀式を行う
- 頑張りすぎず、家族みんなが笑顔で過ごせるような、簡易的なお七夜の検討も大事
お七夜を「する」「しない」は家庭それぞれのかたちでOK♪
大切なのは、赤ちゃんの誕生を喜ぶ気持ちと、ママ自身を大切にすることです。
あなたらしいスタイルで、心あたたまる一日を過ごしてくださいね!
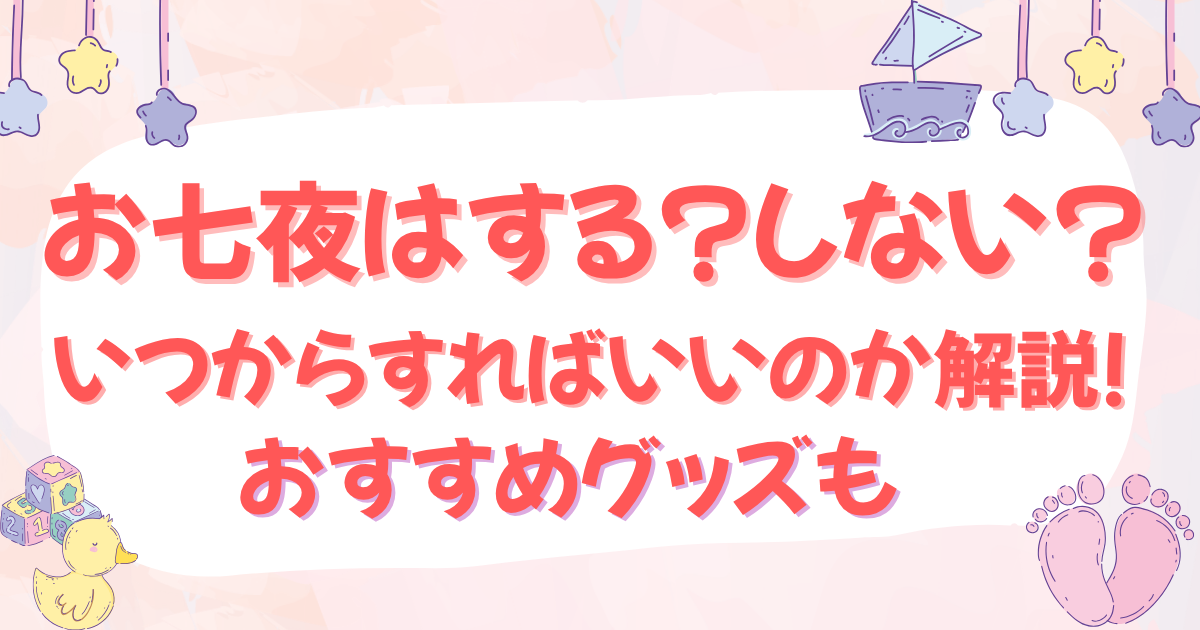
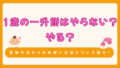
コメント